能登畠山家武将総覧
(ま行〜わ行)
| 真舘 氏矩(まだち うじのり) |
?-1550? |
| 真舘氏寧の子。畠山義続に仕える。能登天文の内乱において長続連とともに天神河原へ出陣するが、討死したらしい。 |
詳細情報なし |
| 真舘 好久(まだち よしひさ) |
1362-1427 |
| 土田氏好の子。羽咋郡土田荘(志賀町)の土豪で、康応年間に同地に父・氏好とともに移住し真館姓を名乗る。子孫は鹿島郡の豪族となる。享年67歳。 |
詳細情報なし |
| 松百 越後(まつど えちご) |
生没年不詳 |
| 実名不詳。弘治の内乱には義綱方の将として「平加賀続重」と「甲斐庄駿河家繁」とともに名前が見え、1557(弘治3)年に温井方の将・山庄直秋と合戦している。(小田吉之丈『七尾城主畠山記』1928年、P78より)。松百氏は鹿島郡奥原保松百(七尾市)を知行した畠山氏の家臣である。戦国後期に同地は能登畠山氏家臣・二本松氏の所領となっている。 |
詳細情報なし |
| 松波 義龍(まつなみ よしたつ) |
?-1572 |
| 常陸介。畠山常重の嫡男。松波畠山氏5代当主を継承するにあたり、奥能登の有力豪族松波氏を相続する。 |
詳細は松波特集 |
| 松波 義親(まつなみ よしちか) |
?-1577 |
| 常陸介。畠山義綱の三男。松波畠山家6代当主。謙信の侵攻時、七尾城が落城する脱出して松波城に帰還し、再起を図ろうとした。ところが追っ手が松波まできて敗れて自害した。 |
詳細は松波特集 |
| 松波 義行(まつなみ よしゆき) |
生没年不詳 |
| 丹波守。松波義親の弟。堀松城代。 |
詳細は松波特集 |
| 松山 伯耆守(まつやま ほうきのかみ) |
生没年不詳 |
| 『能登畠山史要』によると1576年の謙信侵攻の際、畠山方の将として七尾城内の守りについている。 |
詳細情報なし |
| 馬淵 綱重(まぶち つなしげ) |
生没年不詳 |
| 彦三郎。畠山義綱に仕えた。寺社領の代官として活躍したのが確認できる。 |
詳細情報なし |
| 丸山 梅雪(まるやま ばいせつ) |
生没年不詳 |
| 初め清三郎家長。畠山宗家に仕えていたが、1513年に能登に下向し、義元、義総に仕えた。文化的全盛の義総政権期で、茶の湯を好み名物「はく雲」の葉茶壷やさした香炉などを所持していた。 |
丸山梅雪特集 |
| 万行 某(まんぎょう ぼう) |
生没年不詳 |
| 鹿島郡万行の地頭。天正元年(1572)に畠山家臣に「万行殿」の名がある。 |
詳細情報なし |
| 三階 家吉(みかい いえよし) |
生没年不詳 |
| 備後守。1481年に能登島向田代官に家吉の名がある。 |
詳細情報なし |
| 三引 某(みつひき ぼう) |
生没年不詳 |
| 実名不詳。天文年間(1532〜1555)の頃、長家の家臣であったと言う。三引氏は、七尾市田鶴浜町に館を構えていたと思われる。(高井勝己『石川県城郭総覧』1981年,自費出版,P257より) |
詳細情報なし |
| 三宅 三郎(みやけ さぶろう) |
生没年不詳 |
| 仮名三郎。右衛門尉。実名不詳。満慶に仕えた。1408(応永15)年の能登畠山家創設に伴い、河内から能登に下向した譜代の臣。しかし、1421(応永21)年には三郎の所領が闕所地になっていることから、没落したか死去していると思われる。 |
詳細情報なし |
| 三宅 小三郎(みやけ しょうざぶろう) |
?-1528 |
| 三宅氏庶流小三郎家の人物。仮名小三郎。実名不詳。小三郎続長の父。畠山義総に仕え寵愛を受ける。1525年(大永5)年には宗碩と共に禁中の月を拝観したり、1528(大永8)年5月には尊円親王手本を買得して、三条西実隆の証明を依頼し、送付してもらったらしい。かなりの文化人であったことが伺えるが、1528年8月2日に死去した。なお、実隆は義総に同情の念を寄せたらしい。 |
詳細情報なし |
| 三宅 忠俊(みやけ ただとし) |
生没年不詳 |
| 三郎右衛門尉。畠山義統の近臣。畠山氏直領の珠洲郡方上保の代官を務める。1479(文明11)年に京都清水寺再興の為の募縁があったとき、能登では忠俊と温井孝宗がこれに応じ奉加している。この頃にそれだけ忠俊が経済力を持っていたという徴証である(『成就院文書』)。1499(明応8)年には、東寺からの「屋形巻数披露」や総持寺からの書状について、病に伏している屋形(畠山義統)の代わりに、書状を返信していることから、かなり政権の中心に近い人物であったことが想起される。歌人の招月庵正広が能登に来た時には1481(文明13)年に忠俊の所で歌会を一座もうけているなど文化にも力を入れていた。 |
詳細情報なし |
| 三宅 続長(みやけ つぐなが) |
生没年不詳 |
| 三宅氏庶流小三郎家の人物。仮名小三郎。畠山義総・義続・義綱・義慶に仕える。小三郎の子。崎山城城主。鳳至郡宇出津に本拠を持つ土豪。弘治の内乱では、一族が温井方に組する中、ひとり義綱方に属した。1563(永禄6)年には、出羽から馬4疋を運送する為の船子24人(1人につき80文宛)出銭催促を奉行人からされている。 |
詳細情報なし |
| 三宅 綱久(みやけ つなひさ) |
生没年不詳 |
| 右衛門尉。次郎。畠山義綱に仕える。弘治の内乱では温井方に組し、義綱と対立。弘治の内乱の第2次メンバーの主軸として活躍したが、義綱方に寝返った。 |
詳細情報なし |
| 三宅 俊景(みやけ としかげ) |
生没年不詳 |
| 八郎四郎。弘治の内乱で温井方に組し、義綱と対立。弘治の内乱の第2次メンバーの主軸として活躍。しかし、第3次メンバーとして知られない事から、その間に没したもの(戦死ヵ)と思われる。「俊景」の「俊」の字は、弘治の内乱第1メンバーの傀儡総大将畠山晴俊の偏諱かと思われる。 |
詳細情報なし |
| 三宅 俊長(みやけ としなが) |
?-1531 |
伊賀守。忠俊の子。畠山義元・慶致・義総に仕える。1500(明応9)年の義元守護職罷免に乗じて、遊佐統秀とともに畠山義統の次男・慶致を擁立し、その政権の中枢をなした。1508(永正5)年義元・慶致が和解し義元が守護に復帰すると、俊長は義元派の家臣・隠岐統朝と並び実力を持った。1513(永正10)年の能登の内乱では鎮圧に努力した。1531(亨禄4)年の加賀津幡の合戦において戦死した。
義総政権においても重用されたようで、能州に下向した冷泉為広の門人となった者のひとりに「三宅伊賀」の名前が見える。 |
詳細情報なし |
| 三宅 長盛(みやけ ながもり) |
?-1582 |
| 備後守。温井総貞の子。三宅総広の養子となる。弘治の内乱で兄温井景隆と共に義綱に抵抗する。永禄九年の政変を契機に帰参。義慶に仕え年寄衆に列す。七尾城落城後は投降し、謙信の家臣となる。後、反上杉となって遊佐続光らの七尾城占拠に加わるが、織田勢力が能登に入ると逃れたが、再起を図って佐久間盛軍の堀田帯刀正秀に討ち取られた。 |
詳細情報なし |
| 三宅 総賢(みやけ ふさかた) |
生没年不詳 |
| 彦次郎(影次郎?)。一説には総堅。畠山義総・義続・義綱に仕える。1548(天文17)年に「「禪林宋吉大姉 (ぜんりんそうきつだいし)」という女性を供養するために石塔を建てていることが初見である。この銘文は2014(平成26)年に解読されたものである。その後、大槻・一宮の合戦と七人衆抗争では温井方に組し勝利した。しかし、弘治の内乱では温井・三宅氏の一族の中では唯一義綱方に従い奮戦した。長家史料である「長伝書」によると、1561(永禄4)年、に長続連邸で行われた義綱歓待に総賢も参列し、義綱に房つきの太刀1振りを献上したとされている。永禄九年の政変で義綱が追放されても、義綱に従い近江に向かった。能登御入国の乱にも参加し、義綱軍の別働隊率いて善戦。 |
詳細情報なし |
| 三宅 総広(みやけ ふさひろ) |
生没年不詳 |
| 筑前守。三宅俊長の子。畠山義総・義続に仕える。1次・2次七人衆に列し、総貞派の臣となる。大槻一宮の合戦でも総貞に組し、勝利した。 |
詳細情報なし |
| 三宅 宗隆(みやけ むねたか) |
?-1582 |
| 三宅氏庶流小三郎家の人物。仮名小三郎。三宅続長の子。鳳至郡崎山城主。七尾城落城後は謙信に使える。反上杉となって遊佐続光らと謀って七尾城を占拠するが、信長の臣が能登に入国すると越後に逃亡。再起を図るが、前田家臣佐久間盛政に殺される。 |
詳細情報なし |
| 三善 一守(みよし かずもり) |
1547-1615 |
| 石見守。小浦一守とも称す。越中国池田(小浦山)城主。 |
三善一守特集 |
| 三善 光康(みよし みつやす) |
?-1567 |
| 石見守。一守の父。能登畠山氏に属して戦功があり、一ニ葉菊の紋を与えられたという。 |
詳細情報なし |
| 八代 因幡(やしろ いなば) |
生没年不詳 |
| 実名不詳。因幡守。八代氏の一族であるが系譜関係不明。『能州國司畠山殿傳記』によると、1576年の上杉謙信の能登侵略の際、畠山方の武将として「物頭・八代因幡等」と記している。系譜関係がわからないので、八代嫡家(安芸守俊盛の系統)かどうかわからないが、1569(永禄12)年俊盛が長続連や温井景隆に対して挙兵した鶏塚の合戦で、少なくとも八代家一族は完全に追放されたり没落したりしたのではなく、畠山家にまだ臣従していたことがわかる。 |
詳細情報なし |
| 八代 俊盛(やしろ しゅんせい) |
?-1569 |
| 実名不詳。安芸守。弘治の内乱の義綱方への援軍として能登に入国し、能登畠山家に復す。義綱追放後は義慶に仕えるが、温井旧領を得ていた為、温井復帰後徐々に立場が弱くなり、1569(永禄12)年鶏塚で挙兵したが義慶方の長続連らの軍勢に討ち取られた。 |
八代俊盛特集 |
| 八代 外記(やしろ げき) |
?-1569 |
| 実名不詳。外記。八代俊盛の嫡子。外記の妻は長綱連の娘・玉であると言う。1569(永禄12)年11月、父俊盛が能登鶏塚で挙兵すると行動を共にし、義慶方の長続連らの軍勢に敗れ戦死する。 |
詳細情報なし |
| 八代 肥後(やしろ ひご) |
?-1580 |
| 実名不詳。肥後守。八代俊盛の弟。1569年11月、兄俊盛が能登鶏塚で挙兵すると行動を共にし、義慶方の長続連らの軍勢に敗れ越後に逃亡する。畠山家滅亡後の1580(天正8)年、温井・三宅氏らが中心となって運営する政権に弟越中守(主水ヵ)と共に参加し、織田信長に対峙する。しかし、信長の援軍を得た長連竜に菱脇合戦に負けて敗死する。 |
詳細情報なし |
| 八代 主水(やしろ もんど) |
?-1580 |
| 実名不詳。八代俊盛の弟。1569年11月、兄俊盛が能登鶏塚で挙兵すると行動を共にし、義慶方の長続連らの軍勢に敗れ越後に逃亡する。畠山家滅亡後の1580年、「八代越中」という人物が、温井・三宅氏らが中心となって運営する政権に兄肥後と共に参加し、信長の援軍を得た長連竜に菱脇合戦に負けて敗死するが、これは主水の可能性もある。 |
詳細情報なし |
| 山庄 直秋(やまじょう なおあき) |
生没年不詳 |
| 藤兵衛。温井紹春(総貞)の家臣。長氏庶流の一族とも言われる(和嶋俊ニ『奥能登の研究』354頁より)。1558(永禄元)年に弘治の内乱の温井方の老臣として登場し、五百人の兵を率いて敷波に出陣し、苅田(収穫間近の田んぼの稲を勝手に刈ってしまう行為)をしていた。畠山軍と遭遇し合戦となると、温井に使いを出して援軍を得て合戦に勝利している(小田吉之丈『七尾城主畠山記1928年、P78より)。 |
詳細情報なし |
| 山田 左近助(やまだ さこんのすけ) |
生没年不詳 |
| 実名不詳。長氏の被官。山田城主。長家の被官ということで、弘治の内乱では義綱方にあったが、後に温井方に寝返る。山田氏の没収地は桜井壱介に与えられた。 |
詳細情報なし |
| 吉見 統範(よしみ むねのり) |
生没年不詳 |
| 孫太郎。南北朝時代に能登守護となった吉見氏の末裔で能登畠山家の臣。畠山義統に仕える。1470(文明2)年と1478(文明)年にも統範は総持寺へ櫛比庄を寄進している(総持寺文書)。 |
詳細情報なし |
| 吉見 統頼(よしみ むねより) |
生没年不詳 |
| 兵部大輔。南北朝時代に能登守護となった吉見氏の末裔で能登畠山家の臣。畠山義統に仕える。1470(文明2)年「吉見兵部大輔統頼」が総持寺に富来院を寄進している(総持寺文書)。 |
詳細情報なし |
| 遊佐 宗円(ゆさ そうえん) |
?〜1555? |
実名不詳。信濃入道。畠山義続に仕える。能登天文の内乱(1550年)に参加し、能登国内に甚大な被害を与えた責任を取り、温井総貞、遊佐四右、遊佐信州(後の宗円)、伊丹某と共に落髪し入道して宗円と名乗る。その後、第1次七人衆に列し、総貞派の家臣として行動。大槻・一宮の合戦では一族の遊佐続光に味方せず、温井方に組す。1554(天文24)年7月には紹春や神保総誠、長続連らと共に本願寺に当年の礼として「太刀・馬代」として500疋を献上している(『天文日記』より)。この銭を献上した他のメンバーをみると、相変わらず宗円の地位が高いのがわかる。
坂下喜久次氏は著書『七尾城と小丸山城』P.437で遊佐宗円は珠洲郡飯田郷領主で飯田城を築き、1517(永正14)年冷泉為広に師事した遊佐孫六ではないかと指摘している。
年次未詳だが、宗円が珠洲郡西方寺領の税の進納についての文書を発給している(松若州あて)。しかし、弘治の内乱が始まった後の1555(弘治元)年閏10月には、畠山義綱の命を受けた遊佐続光が西方寺領の税について禅経坊に対しての文書を発給している。このことから宗円は1555(弘治元)年の閏10月までには死去したのではないかと考えられる。 |
詳細情報なし |
| 遊佐 右衛門尉(ゆさ うえもんのじょう) |
生没年不詳 |
| 実名不詳。能登御入国の乱に義綱軍の馬廻衆として参戦。府中の池田要害に義綱は遊佐孫右衛門尉を配置した。能登遊佐嫡家の遊佐忠光が「孫右衛門尉」を名乗っている事から、あるいは能登遊佐嫡家の人物かもしれない。 |
詳細情報なし |
| 遊佐 越中守(ゆさ えっちゅうのかみ) |
生没年不詳 |
| 実名不詳。1497(明応6)年に、能登国土田庄の公用銭について京都加茂社と相論が起こった時、年寄衆の隠岐統朝が京都に伊勢上野守と共に使者として派遣している。 |
詳細情報なし |
| 遊佐 熊石丸(ゆさ くまいしまる) |
生没年不詳 |
| 畠山義綱に仕えたヵ。1558(永禄元)年に岩蔵寺に武運長久・子孫繁昌を祈願しするため町野庄の行内名の所領の田を諸役免除で寄進した(石倉比古神社文書)。 |
詳細情報なし |
| 遊佐 忠光(ゆさ ただみつ) |
生没年不詳 |
| 美作守。右衛門尉(文書には「遊佐孫右衛門尉忠光」と名が記されている)。畠山義忠に仕える。義忠政権において守護代に就任。越中阿努荘の代官も兼ねていた。守護代として、1445(文安2)泊弥次郎に知行の一部を御料所とすることを伝えたり(筒井文書)、同年、永光寺への制札を与えている(筒井文書)。 |
詳細情報なし |
| 遊佐 続光(ゆさ つぐみつ) |
?-1582 |
| 美作守。義続。義綱・義慶・義隆・春王丸に仕える。離反帰参を繰り返すが、常に政権の中枢にあった。謙信の侵攻では、内応し七尾城開城して上杉の臣となる。後、反上杉として七尾城を占拠し、信長帰服する。しかし信勢力によって捕らえられ斬首される。 |
遊佐続光特集 |
| 遊佐 秀倫(ゆさ ひでみち) |
生没年不詳 |
| 左馬允。畠山義総の近臣。越後上杉氏との交渉役にもなったことも。 |
詳細情報なし |
| 遊佐 秀盛(ゆさ ひでもり) |
?-1531? |
右衛門尉。遊佐統秀の子。畠山義総に仕え、遊佐の嫡家にかわって守護代に抜擢された。越中永正の乱では、義総の参謀役を勤めた。また、1517(永正14)年から1518(永正15)年に能州に下向した冷泉為広の門人となっており、一定の文化水準があったと思われる。
1531(享禄4)年を境に守護代を息子の秀頼と交代しており、同年にあった加賀津幡の合戦で戦死したのではないかとも考えられている。 |
詳細情報なし |
| 遊佐 秀頼(ゆさ ひでより) |
生没年不詳 |
| 豊後守。秀盛の子。畠山義総に仕え、守護代にもなった。他にも、足利義晴に対し尾州畠山氏(河畠山氏政長流)の畠山稙長の進退についての義総の交渉の奏者となったり、度々の将軍・足利義晴動座で不安定な中、若公様(義昭)誕生の御礼の交渉をしたり、重要な対幕府外交を担っている政権中枢の人物と言える。 |
詳細情報なし |
| 遊佐 総光(ゆさ ふさみつ) |
生没年不詳 |
| 美作守。亨禄の頃の人物。美作守の官途と遊佐嫡家の継字「光」から遊佐嫡家の人物であろう。また恐らく「総光」の「総」の字は義総の偏諱であろう。 |
遊佐総光特集 |
| 遊佐 光貞(ゆさ みつさだ) |
生没年不詳 |
| 右衛門尉。1429(正長2)年若山庄領の年貢未進分を送った「遊佐五郎孫右衛門尉光貞」の名の文書が見える。この前年若山庄の年貢は守護代の遊佐祐信が送っていたのであるが、この年は光貞が送っている。系譜関係は不明だが、名前の「光」という字と、「孫右衛門尉光貞」という遊佐忠光が名乗っていたのと同じ官途から、遊佐祐信(基光)の一族ではないかと思われる。年代からすると、あるいは弟ヵ。 |
詳細情報なし |
| 遊佐 統忠(ゆさ むねただ) |
生没年不詳 |
| 1509(永正6)年、永光寺(羽咋市)に若部保から給米と年貢銭を寄進している。この統忠の行動は、1456(康正2)年に遊佐忠光が、1562(永禄5)年に遊佐続光特集が行っていることから、統忠は遊佐の美作守(嫡家)家の出自ではないかとされている。 |
詳細情報なし |
| 遊佐 統秀(ゆさ むねひで) |
生没年不詳 |
| 美作守。遊佐忠光の子。義統政権下で守護代を務める。義統在京時は相当な力を持っていたようである。1500(明応9)年に義元が守護を罷免されると、義統の次男・慶致を擁立。その守護代として実権を握った。のち両者に和解が成立すると、慶統派の家臣筆頭として実力を保った。 |
遊佐統秀特集 |
| 遊佐 盛光(ゆさ もりみつ) |
?-1582 |
| 孫太郎。四郎右衛門尉。綱光。遊佐続光の子。最初当主・義綱の偏諱を受けて「綱光」と名乗るが、永禄九年の政変後は義慶に仕えて「盛光」と名乗る。父から後に家督を譲られるものの、依然として父が実権を握り印象が薄い。上杉侵攻後謙信に仕え、七尾城占拠後には父と共に逐電するも斬首される。 |
遊佐盛光特集 |
| 遊佐 祐信(ゆさ ゆうしん) |
生没年不詳 |
実名基光。仮名孫太郎。美作守。入道して沙弥祐信。畠山基国が1402(応永9)年から一年半山城守護になった時、守護代となった。1409(応永16)年まで河内畠山家の家臣としての活動がしられる。しかし、翌1410(応永17)年頃には能登国守護代の仕事として永光寺領への禁制命令文書を出しており、この年までに能登畠山家に移り、入道したと思われる。
能登畠山家初代当主・畠山満慶時代に能登守護代を務めるが、自身も在京し在国した祐信の被官である池田主計入道(この被官も河内から連れてきた者)に実務を担当させていた。守護代としての活動は、1426(応永33)に池田主計入道に対する寄進地下知状、1428(正長元)守護代官請領である若山庄の年貢20貫を送った文書などが残っている。 |
詳細情報なし |
| 和田 彦次郎(わだ ひこじろう) |
生没年不詳 |
| 実名不詳。信章や光章などの系譜も不明。1513(永正10)年から続く能登永正の内乱において、1514(永正11)年7月に天野俊景らと共に本領を出津して船で七尾へ来城し、畠山義元の身の廻りの守備を勤めた。 |
詳細情報なし |
| 和田 信章(わだ のぶあき) |
生没年不詳 |
| 和田氏は羽咋郡志雄の在地領主で、能登畠山氏の被官である。1441(永亨3)年に信章の祖父・紹賢が永光寺仏殿の修理料をまかなう為に田を寄進した文書が残っている。 |
詳細情報なし |
| 和田 光章(わだ みつあき) |
生没年不詳 |
| 和田信章の子とも言われる。1463年に寄進した土地は、畠山義統によって安堵されている。和田信章、光章父子はいずれも得田氏の通字である「章」を称していることから、得田氏とつながるものがあったと推察される。 |
詳細情報なし |
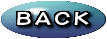
武将総覧の目次へ戻る
武将総覧あ行〜か行へ
武将総覧さ行〜た行へ
武将総覧な行へ
武将総覧は行へ
Copyright:2021 by yoshitsuna hatakeyama -All Rights Reserved-
contents & HTML:yoshitsuna hatakeyama