弘治の内乱
[1555年〜1560年]
畠山義綱軍VS温井・三宅連合軍
- ●原因
- 大槻一宮の合戦で活躍した温井紹春(総貞)は、七人衆の中で筆頭の地位を握り、次第に家中で専横になってきた。『長家家譜』などの長家資料によると、紹春の行動は遊佐続光と違い下剋上的行動にまで発展したので、1555(弘治元)年、大名権力回復を目指す9代当主義綱の幽閉を謀る。しかし、長続連が事前に紹春の動きを察知し義綱に報告した。義綱はこれ以上紹春の動きは見過ごせないと判断、紹春を連歌の会と偽って飯川邸に呼び出し暗殺した(注1)。これに反発した、温井家は挙兵。血縁関係にある三宅も加勢し大規模な内乱へ発展した。
|
畠山義綱軍 |
温井・三宅連合軍 |
| 勝敗 |
WIN |
LOSE |
| 兵力 |
畠山義春・神保周防守隊千余人
三宅宗隆・畠山将監隊八百人
(永禄元年頃))
<『七尾城主畠山記』P77> |
三千人(永禄元年頃)
<『七尾城主畠山記』P77> |
| 本拠地 |
七尾城 |
鹿島郡勝山城 |
| 支配域 |
七尾城・奥能登・中能登(内浦) |
口能登(外浦) |
| 支援者 |
長尾景虎 |
加賀一向一揆・武田晴信 |
| 総大将 |
畠山義綱 |
畠山晴俊(傀儡)→戦死 |
| 主力 |
飯川光誠
長続連
笠松但馬守
遊佐続光(1555年閏10月帰参)
神保周防守
三宅続長(注2)
八代俊盛
平続重
甲斐庄家繁
山田左近助(後に温井方に転身) |
温井続宗→戦死
温井続基
三宅総広→戦死
三宅綱賢(後に義綱方へ転身)
三宅綱久
神保総誠→戦死
温井綱貞→戦死
三宅俊景→戦死
温井景隆
温井続基 |
|
 |
●経過
- 1555年9月下旬、温井三宅連合軍(以下反乱軍)が口能登を占領。一帯を占領支配する。
- 義綱軍は、七尾湾の制海権と奥能登を維持し、七尾城籠城の継続を経済的・軍事的に可能にして防戦する。
- (年次不詳だが1555年〜1556年頃)反乱軍が勝山城を本拠とする。
- 1556年1月、義綱三宅や伊丹らに木材の徴用を命ずる(諸橋文書)。防衛のため用い七尾城を補強・改修したと思われる。
- 同年2月、飯川光誠を通じて笠松新介(但馬守))が七尾城に入城し兵力増強に成功する。
同年9月、温井方が阿岸本誓寺を味方につける(阿岸本誓寺文書)。
- 1557年1月、義綱が長又次郎(布施長氏)に篭城の際用立てした兵糧を返却し、知行を与えた(長文書)。兵糧を返却したと言うことはこの頃には戦況が少し改善したのだろうか。
- 同年2月、義綱の使者遊佐続光(義綱が帰参させた)が長尾景虎に援軍を頼むが、景虎信州への出兵のため兵糧のみの援助を伝える(『上杉家文書』)。
- 1557年6月2日、反乱軍が義綱軍の八代俊盛が拠点とするの越中国氷見・湯山城を陥落させる。
- 同年7月、椎名宮千代の援助を受けた八代俊盛が舟で富山湾を渡り七尾城に入城する。
- 同年、義綱が弟・畠山義春と神保周防守を率い、兵千人で出陣する(『七尾城主畠山記』P77)。
- 1558年4月、義綱は六角氏を通じて本願寺の温井への合力停止を要請する→本願寺の温井への援助が弱まる。
- 同年春頃、義綱軍攻勢に出る。晴俊の立て籠もる勝山城を攻略→反乱軍の一時沈静化
同戦闘で畠山晴俊・温井続宗・神保総誠・三宅総広ら討死→残党は加賀へ退去。
- 同年7月初旬、反乱軍・温井綱貞らが再び能登へ侵攻する。
- 同年9月、義綱軍・山田左近助が温井方へ寝返る。
- 1559年3月、反乱軍、一向一揆を率いて攻め込むが長続連に討たれる→反乱軍は押水まで後退
- 1560年初、温井残党を能登から一掃。
ちぇっくぽいんと!
「温井・三宅連合軍の戦略」
☆温井・三宅連合軍主軸の移り変わり
反乱軍となった温井・三宅連合軍が外浦、荒山峠を占拠したには理由がある。まず外浦の占拠については、日本海の制海権を確保する事と、海上交通の補給路としての利権を見越してのことである。また荒山峠を抑え、氷見地方を占拠し荒山峠ににらみを効かせる勝山城に本拠を置いた理由としては、陸路としての氷見−七尾間、羽咋−七尾間の連絡・物流を断つ事にあった。これにより、七尾城を孤立させ、陥落させようと思った戦略であったと思われる。しかし、実際には、義綱軍が奥能登の基盤を維持したため、七尾−奥能登間の連絡・物流を断つ事ができず、七尾城を孤立させる事ができなかったのである。結局は義綱軍に敗れる事になったが、初期反乱軍(上記表で言えば「1次メンバー」)がまがりなりにも三年も持ちこたえた背景には、海路と陸路という物流の流れを抑えていた強みがあったに相違ないと私は思っている。
|
1次メンバー |
2次メンバー |
3次メンバー |
| 時期 |
1555年〜1558年春 |
1558年7月〜 |
1559年〜1560年初 |
| 総大将 |
畠山晴俊→戦死 |
|
|
| 主軸 |
温井続宗→戦死
神保総誠→戦死
三宅総広→戦死
三宅綱賢→義綱方に転身 |
温井綱貞→戦死
三宅綱久
三宅俊景→戦死 |
温井孝景
三宅慶甫
三宅綱久 |
| 拠点 |
勝山城 |
福水に陣を置く |
|
- ●合戦の影響
- 温井軍の反乱によって、反乱分子が抜けた畠山家中では、畠山義綱のイニシアチブが確立する。その結果、義綱−飯川光誠という支配体制ができあがった。この体制が出来あがったにも関わらず畠山七人衆が抵抗しなかった事を考えると、第2次七人衆が実質的に総貞を中心に動いていた事がわかる(畠山七人衆体制と権力闘争参照)。こうして弘治の内乱は、義綱の専制支配を確立させた。大名権力が強化された結果、重臣達の利害の対立からの内乱は一応おさまり、能登に一瞬の平和が訪れた。この頃の平和を示す資料として、長続連が1561年に畠山義綱を私邸で歓待したり(長続連の歓待からみるもの参照)、義綱が将軍義輝に年始の贈り物を再開した事が知られる。しかし、一層の権力拡大を狙う義綱は、大名権力の強化に必要な「重臣権力の削減」と「権力基盤」としての重臣からの支持の取りつけという矛盾を抱えた。結局、そのバランスを保つ事ができずに、大名権力強化の反発から義綱は永禄九年の政変で重臣達に当主の座を追われて失脚した。こうして、能登の平和は崩壊し再び混沌とした政治状態が続いていった。
(注釈)
(注1)義綱の紹春暗殺は、無かったとする説もある。「能登弘治の内乱基礎的考察」(『国史学』122号)で東四柳氏が指摘したものである。義綱の紹春暗殺は通説であって、確証を得たものではないと指摘する。この内乱が起こった要因は、何らかの要因で紹春が死去し(病気ヵ)それを契機として義綱が専横な温井派の排除を画策したのではないかと指摘している。
(注2)反乱軍が温井・三宅連合軍であるのに、三宅続長が義綱軍にいるのが面白い。三宅家が一枚岩ではなかった証拠となろう。それは、最初温井方についた三宅綱久が、後に義綱方に寝返っていることからも想像できよう。
- 参考文献
- (共著)『中島町史通史編』中島町,1996年
(共著)『七尾市史通史編』七尾市,1974年
(共著)『羽咋市史』羽咋市,1973年
佐伯哲也「能州勝山城址について-能登国の大城郭に関する若干の考察-」『石川県考古学研究会々誌』41号
東四柳史明「畠山義綱考」『国史学』88号,1972年
東四柳史明「能登弘治の内乱の基礎的考察」『国史学』122号,1984年
etc・・・
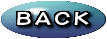
合戦記録の目次へ戻る
Copyright:2007 by yoshitsuna hatakeyama -All
Rights Reserved-
contents & HTML:yoshitsuna hatakeyama
