長続連の義綱歓待からみるもの
はじめに
畠山義綱が専制支配を確立した1560(永禄3)年から永禄九年の政変で追放される1566(永禄9)年までの6年間は、能登の最後の安定期であった。家中最大の対立派閥の温井・三宅派を5年の歳月をかけて追放し(弘治の内乱)、戦乱続く戦国時代の能登に文化の息吹が再び現れた時期であった。畠山義総の時代には文化的業績が史料上でも色々残っているが、晩年の畠山文化についてはほとんど知られていない。その頃の文化水準を知る資料に、1561(永禄4)年長続連が自邸で畠山義綱を歓待した記録が長家の史料がある。これは晩年の畠山文化を知ることが出来る数少ない貴重な資料である。本稿ではこの史料を基に、永禄期の畠山文化の一端を探ってみたい。なお、筆者は文化面に疎い為、中世文化に精通した林六郎光明殿(六郎光明の屋形@管理人)に全面的にご協力を頂いた。この場を借りて御礼申し上げたい。さらに2016(平成28)年に発刊された『加能史料ⅩⅣ』に詳細が記述されたため、さらに補筆を加えた。
(1)歓待の記録
片岡樹裏人氏の著作『七尾城の歴史』によると、歓待の記録は「長伝書」に記録されているという。原本が失われており、その写本である長家に残る記録に長続連の歓待が書いてあると言う事は、誇張した表現があると思われるが、他に頼る資料がないことから、この資料を持って永禄期の畠山文化を探ることとしたい。まずは、その関係部分を抜粋する。なお※印については註釈(義綱の訳)としてメニューついて(一部Yahoo!辞書を参照しました)や、『能登畠山文化源流をゆく2018年度調査報告書』(以下『源流をゆく2018』略)などを参考にした。
「長家文書雑記」(『新修七尾市史』七尾城編より抜粋) ※印の註釈については義綱の加筆
永禄四年(正月)続連公御亭江畠山義則(綱)公御招請之献立
式三献前
| 御朝食 |
御本膳 |
|
|
※朝食からの主君の御成(家臣の家へ行く)は珍しい。だいたいは午後から始まるもの(『源流をゆく2018』P.96) |
| 塩引き |
やき物 |
御汁こまこきり |
|
※塩引(しおびき):塩漬けにした魚。(例、塩鮭など)
※こま(胡麻)こきり(小切) |
| 牛房 |
さかひて
このわた |
てしほ
御めし |
|
※さかひて(酒浸)
※てしほ(手塩):食膳に添えて適時使った焼塩。
※海鼠腸(このわた):ナマコの腸管で作った塩辛。
※御めし:ご飯のことヵ。 |
| 二献 |
|
|
|
|
| からすミ |
鯉焼 |
|
|
|
| 蛸 |
さしミ
すし |
うしほに |
|
※蛸:タコ
※さしミ(刺身)
※うしほに(潮煮):タイなどの白身の魚のぶつ切りを塩味のみで煮込んだ煮物。 |
| 三献 |
|
|
|
|
| 貝蚫 |
いもこみ |
ほやひや汁 |
|
※貝蚫・あわひ:アワビ
※いもこみ:芋籠:→いもかご:ジャガイモを籠状の形に揚げたもの。
※ひや汁:冷や汁→冷汁。魚介を入れた味噌仕立ての汁(『源流をゆく2018』P.100) |
| かまほこ |
御ひき物 |
しいたけ
白鳥 |
|
※かまほこ:かまぼこ |
| 海月 |
|
|
|
※海月:くらげ |
| にし |
|
|
|
※にし(螺・辛螺):巻き貝の一種。アカニシ・ナガニシ・タニシなど。 |
| 御菓子九種 |
山のいも
から島のり
ふのにくし |
ひらくり
から花
こふ
かしかき |
くるミ |
※お菓子九種:昔はくだもののことを指した。
※山のいも:山芋
※ひらくり:平栗
※から島のり:中島町の島でとれる海苔
※から花:造花(若しくは唐花?)
※ふのにくし:麩濁→麩の小串ヵ。
※こふ:こんぶ→昆布
※かしかき:こしかき→干し柿ヵ |
| 初献 |
|
|
|
|
| やき鳥 |
|
|
|
※やき鳥:この時代はキジの肉が多い。 |
| 雑煮 |
くしこ
やきくり
すかあわひ
みミ塩 |
|
|
※串海鼠
※すかあわひ:酢貝鮑→アワビの酢の物
※みミ塩:手塩のようなものヵ(『源流をゆく2018』P.101) |
| 五種 |
かつうを
むすひこふ |
|
|
※かつうを:鰹(かつお)のこと。
※むすひこふ:むすびこぶ→結び昆布 |
| 二献 |
|
|
|
|
| くま引 |
|
|
|
※くま引→熊引→鮪の干物。(『源流をゆく2018』P.101) |
|
あつ物 鮒 |
|
|
※あつ物(羹・熱物):魚・鳥の肉や野菜を入れた熱い吸い物。 |
| つめた |
|
|
|
※つめた:ツメタ貝(ツブニシ) |
| 三献 |
|
|
|
|
| するめ |
|
|
|
|
|
あつ物 ひし喰 |
|
|
※ひし喰・ヒシクイ:鴨(カモ) |
| いさゝ |
|
|
|
※いさゝ(いささ):いさざ。ハゼ科の小魚。 |
| 四献 |
|
|
|
|
| むしむき |
まつかつを |
|
|
※むしむき:蒸麦→うどん(『源流をゆく2018』P.101)
※まつかつを:まつかつお→まかつお→マガツオのことヵ。 |
| 五献 |
|
|
|
|
| ちん |
|
|
|
※ちん:干魚をほぐして辛みをつけ酢で煮たもの(『源流をゆく2018』P.101) |
|
あつ物 鯛 |
|
|
|
| はい |
|
|
|
※はい:蓮根(れんこん)の昔の名前。 |
| 六献 |
|
|
|
|
| やうかん |
舟もり
そへ物 |
|
|
※やうかん:羊羹(ようかん)のことヵ。
※舟もり:舟盛
※そへ物:添え物→「何か書かれてないが、『朝倉亭御成記』ではまなかつおや鴫(しぎ)がみえているから、魚鳥と推定」(『源流をゆく2018』P.101) |
| 七献 |
御湯漬参、 |
|
|
※湯漬・湯漬け(ゆづけ・湯漬):御飯に湯をかけて食べる。 |
| 大はむ |
やき物 |
松百すし |
|
※大はむ:はむ→はも=鱧
※松百すし:七尾の松百の熟れずし(注1) |
| あへませ |
御食ミゝ塩 |
|
|
※あへませ:数種類の和え物のことヵ。 |
| かうの物 |
|
|
|
※かうの物(香の物・こうのもの):野菜を塩・ぬか・味噌・酒かすなどに漬けたもの。漬物のこと。 |
|
海鼠腸・ふくめ鯛 |
|
|
※ふくめ鯛:干した鯛 |
| 二献 |
|
|
|
|
| 魚の子 |
|
|
|
|
| すゝき |
りやう< |
あつめ汁
こゝりとうふ |
|
※すゝき:すすき→スズキ
※りやうく:りゃうりゃう→煎海鼠(いりこ)のこと(『源流をゆく2018』P.102)
※あつめ汁(集め汁): 干し魚(煮干し子/干鮭)や干し野菜(ずいき)、生野菜(ねぎ)、豆腐などを取り合わせたみそ汁。
※こゝりとうふ(こごり豆腐):凍り豆腐。高野豆腐。しみ豆腐のこと。 |
| さしミ |
|
|
|
|
| 三献 |
|
|
|
|
|
御汁 |
|
|
|
| 鮎すし |
ひし喰 |
|
|
|
| 雲雀 |
|
|
|
※雲雀(ひばり):スズメ目ヒバリ科の鳥。 |
| 八献 |
|
|
|
|
| しひのこ |
|
|
|
※しひのこ:しび(鮪)の子(『源流をゆく2018』P.102) |
|
あつ物 |
松かさ煮 |
|
※「鯛の身を鱗形に切、筋違に刀目を入れ湯びき候へば松笠に似る。たれみそなどで煮也」(『源流をゆく2018』P.102) |
| 青なすひ |
|
|
|
※青なすひ:青茄子 |
| 九献 |
|
|
|
|
| 蛸 |
あつ物 |
鶴 |
|
|
| 十献 |
|
|
|
|
| まんちう |
御そへ物
りうさし |
|
|
※まんちう:まんじう→まんじゅうのことヵ。
※りうさし:「龍さし」(『朝倉亭御成記』より)「龍刺」(『三好亭御成記』より)で一般的だが、何かは不明(『源流をゆく2018』P.102) |
| 十一献 |
|
|
|
|
| 干鰤 |
|
|
|
|
|
あつ物 |
こち |
|
※こち(鯒・牛尾魚):カサゴ目コチ科の海水魚。本州中部以南の沿岸の砂泥底にすむ。マゴチ。 |
| はらゝ |
|
|
|
※はらゝ:はらら→「鮭の卵巣の塩漬け。筋子のことである。」(『源流をゆく2018』P.102) |
| 〔十二献離脱ヵ〕 |
|
|
|
| すし |
|
|
|
|
|
あつ物 |
せんはい煮 |
|
|
| 海老 |
|
|
|
|
| 十三献 |
|
|
|
|
| 雲月かん |
そへ物
かさめ |
|
|
※雲月かん:もずくかん→「もずくを使った羊羹の一種であろうか。」(『源流をゆく2018』P.103)
※かさめ:ワタリガニ |
| 十四献 |
|
|
|
|
| 切かまほこ |
|
|
|
|
|
あつ物 |
爪かさね |
|
|
| 生海鼠 |
|
|
|
|
| 十五献 |
此献目ニ御立被成候、 |
|
※此献目ニ御立被成候:「義綱はこの献立で席を立ち休息している」(『源流をゆく2018』P.103) |
| ふり |
|
|
|
※ふり:鰤(ぶり)。 |
|
あつ物 |
蛤 |
|
|
| そほろ具 |
|
|
|
|
| 十六献 |
|
|
|
|
| 佐目 |
|
|
|
※佐目:鮫(サメ)のことヵ。 |
|
あつ物 |
ゑゐ
きも煮 |
|
※ゑゐ:えい→エイ(海鷂魚)のことヵ。 |
| したゝめ |
|
|
|
※したゝめ:したため→「小型の巻貝しただみのことである。」(『源流をゆく2018』P.103) |
| 十七献 |
|
|
|
|
| あいきやう |
|
|
|
※あいきやう:あいぎょう→「鮎の加工品とみられる |
|
あつ物 |
卯の花煮 |
|
|
| たいの子 |
|
|
|
|
| 十八献 |
|
|
|
|
| しいら |
|
|
|
※しいら:スズキ目シイラ科の海水魚。暖海に分布。夏に美味。 |
|
あつ物 |
いさゝ |
|
※いさゝ(いさざ):ハゼ科の淡水魚。シロウオの別名。琵琶湖特産ではあるが、能登でも「いさざ獲り」はさかん。鮨(すし)・飴煮(あめに)などにする。 |
| あわひ |
|
|
|
|
| 十九献 |
|
|
|
|
| 塩かつほ |
|
|
|
※塩かつほ:塩かつお→塩漬けのカツオヵ |
|
あつ物 |
青鷺 |
|
※青鷺(あおさぎ):サギ科の鳥。 |
| ふくの鮨 |
|
|
|
※ふくの鮨:ふぐの寿司。 |
| 二十献 |
|
|
|
|
| さしミ |
|
|
|
|
|
あつ物 |
鮹しひのふと |
|
|
| くる< |
|
|
|
※くる<:くるくる→鱈の内臓の塩辛(『源流をゆく2018』P.103) |
| まきするめ |
|
|
|
|
|
あつ物 |
鯨 |
|
|
| 鰺のすし |
|
|
|
|
| 以上、此外参次第 |
|
|
|
| 御折三十合、 |
御盃台次第、 |
|
|
|
| 御取肴参次第、 |
|
|
|
| 此外押之物参次第於御食籠在之、 |
|
※押之物(おしのもの):種々の料理が出たあとで、花鳥、山水などを形どった作り物の台に盛って出す酒の肴である(『源流をゆく2018』P.103) |
同御進物之目録
| 一、式三献 |
(長ヵ)十郎殿御馬の使、対馬殿(長続連)御太刀の使、直御馬御太刀栗毛、 |
| 一、初献 |
三宅影次郎殿(三宅綱賢)御使、御太刀一腰供房 |
| 一、三献 |
長新次郎殿被参候、盃・香合 |
| 一、五献 |
同源次郎殿御使、三河守殿(長連理)あいそへ、御具足三物・御太刀一腰金ふくりん。 |
| 一、七献 |
神保周防守殿御使、御腰物則盆ニ直 |
| 一、九献 |
御大三之助殿御使、御絵一ふく盆筆馬遠 |
| 一、十一献 |
飯河若狭守殿(飯川光誠)御使、御打刀景光 |
| 一、十三献 |
平左衛門尉六郎殿御使、御長刀法成寺 |
| 一、十五献 |
御大三之助殿御使、御鞍貞宗作 |
| 一、廿一献 |
|
|
以上 |
(後筆)
「右者畠山殿 御進物与相見へ候得共、其事者書記無之、御旧記之儘留置候事、」
| 翁 |
熊木せんざいふ若衆 |
|
さんハサ釘原 此笛彦兵衛 |
| 弓八幡 |
熊木大夫 |
大鞍坊丸 小鞍藤七 |
|
|
大こ弥九郎 笛滝波 |
| 実盛 |
平内大夫 |
同大鞍大津田進助殿 |
|
|
小藤七 太鼓大木 笛滝波 |
| 松風村雨 |
同 |
大鞍三蔵分兵衛 |
|
|
小鞍藤七 笛滝波 |
| 矢立加茂 |
日吉大夫 |
大蔵坊丸 |
|
|
同小鞍若衆 |
| 野々宮 |
平内 |
同大鞍深尾殿 |
|
|
小鞍藤七 |
| 八嶋 |
日吉大夫 |
大鞍大津殿 |
|
|
小鞍藤七 |
| 照君 |
平内 |
同大鞍三蔵 |
|
|
同小鞍藤七 |
| 田村 |
日吉三郎 |
同大鞍深尾殿 |
|
|
同小鞍藤七 |
| 浮舟 |
日吉大夫 |
同大鞍大津殿 |
|
|
同小鞍藤七 |
| 鞍馬 |
熊木 |
同大鞍三蔵 |
|
|
同小鞍弥一 |
| 東岸居士 |
平内 |
大鞍三蔵 |
|
|
同小鞍藤七 |
| 玉かつら |
同 |
大鞍同 |
|
|
小鞍同 |
| 老松出帰 |
熊木 |
大鞍同 |
|
|
小鞍同 |
|
以上 |
|
同狂言 釘原 ひよん介 籾仮源三、
御家之子
| 一番 |
宇留地孫四郎 |
| 二番 |
阿岸新次郎 |
| 三番 |
山田十郎兵衛 |
此木此両人は座敷論を以不罷出候、
老等
| 一番 |
関左近助 |
| 二番 |
中村小二郎 |
| 三番 |
加藤紀三郎 |
| 四番 |
田屋熊千代 |
| 五番 |
関 興三 |
|
(2)登場人物とその背景
主君の御成は午後から行われるのが慣例であるが、この記録によると朝食から行われている。「式三献」(しきさんこん)は、「三献の儀」とも呼ばれ、室町時代に始まると言われる公式の祝賀行事である「盃三献の礼式」である。もともとは朝廷の儀式であったが、それが武士に伝わり、出陣の際や婚礼、式典、接待などの時に行われた。最初の一献には酒を一盃に三度注ぎ、二献には二盃にそれぞれ三度注ぎ、三献には三盃にそれぞれ三度注ぐもので、現代でも和式の結婚式に行う三々九度につながるものである。合戦の前に行われる式三献では、三献めの盃を地面に叩き付けて出陣すると言われている。長続連が何のために畠山義綱を歓待したのか理由は明らかにされてはいないが、弘治の内乱の鎮圧祝いかもしれないし、単に平和になったゆえ、正月の祝いの御膳に義綱を接待し歓待したものかもしれない。
献立の「式三献」にでてくる「対馬殿」は長対馬守続連である。「初献」にでてくる「三宅影次郎殿」は、弘治の内乱で唯一最初から義綱方についた三宅一族の三宅総賢である。「五献」にでてくる「三河守殿」は長三河守連理である。「七献」にでてくる「神保周防守殿」は永禄九年の政変で追放された義綱に追従し能登御入国の乱にも主力として活躍している神保周防守(実名不詳)である。「十一献」にでてくる「飯河若狭守殿」は飯川若狭守光誠である。となると、義綱専制の主力メンバーが集まっている事となる。義綱政権年寄衆となっている遊佐美作守続光の姿が見えないと言うことは、この時期、続光と続連が対立関係にあったために呼ばれなかったのかもしれないし、後世の編纂のため続光の記述をあえて排除したのかもしれない。。
東四柳史明氏(『社寺造営の政治史』において)によると能楽を行った人物で日吉大夫という人物が出てくるが、この人物は能登滞在中の近江猿楽(注2)で畠山義総の頃から庇護を受けていたらしい。日吉大夫は1536(天文5)年には年始の礼で能州に下向している。さらに1537(天文6)年の下向も能登の可能性があり、1550(天文19)年6月20日には「多賀神社文書」に日吉大夫が能州在国したことが知られる。このように度々能登を訪れてる事実は、能登畠山家と積極的な交流があったと推察できる。また、平内大夫と熊木大夫は「能登畠山氏お抱えの猿楽大夫」(『社寺造営の政治史』より)であると言う。この3者の序列は東四柳氏前掲書によると「熊木・日吉大夫(日吉三郎含む)が各四番を演じたのに対し、平内大夫は六番を演じており前述した文録三年の気多社年中神事記録の中でも、熊木大夫の上位に扱われていた。」ということから、日吉大夫>平内大夫>熊木大夫となる。また、1562年(永録5)年の義綱が行った気多社造営の際に行われた猿楽では熊木大夫のみが演じているが、畠山滅亡後には熊木大夫と平内大夫の両大夫が気多社の神事に出仕している。
(3)資料から読み取れるもの

↑写真はクリックすると拡大します。
七尾城を地域が中心となった活用をしようと、「能登の國 七尾城プロジェクト実行委員会」というものが七尾市の矢田郷で立ち上がりました。この団体は、七尾城山という歴史+自然豊かなフィールドを活用すべく、定期的にトレッキングやランニングイベントを企画・運営しており、また古山道復旧や整備維持活動も年間を通して行っているという。さらに、「文化資源活用事業費補助金」(Living
History(生きた歴史体感プログラム)促進事業)によるYouTubeにて動画を作成しており、「七尾城能登畠山饗応御膳」の再現も公開されている。
https://www.youtube.com/watch?v=dDE_mE98btM(←七尾城 能登畠山文化 饗応食の再現)
こちらの動画ぜひ見ていただき再生数を伸ばしていただきたいのですが、なぜ言葉がすべて英語なのでしょうか。この動画をみるのは日本人が多いはずで、料理の内容を詳しく説明してくれれば見る人も多いと思うのですが…。この事業の一環で国際的な観点から英語表記で動画投稿をするという決まりでもあったのだろうか。

上記写真は、「能登の國 七尾城プロジェクト実行委員会」が2020(令和2)年11月21日・22日に行ったメインイベント「七尾城ウォーク&秋の味覚」では、60人の参加者が矢田郷地区コミュニティセンターを出発して城山を登り、調度丸跡の発掘現場を眺めたり、山からの景色を楽しんだ。山頂付近の本丸跡では、七尾城の在りし日の料理を再現した弁当「歴弁」が振る舞われた。戦国大名の畠山義綱が家臣にもてなされた際の献立の記録を基に、七尾市のホテル海望と松乃鮨(まつのすし)、鵬(おおとり)学園高校調理科が考案した料理で、能登ふぐや中島菜など旬の地元食材を使った七品が並ぶ。できれば、イベント以外でも販売してくれないかな…と思う。3000円位かかったとしても、歴史好きの目玉になれば…。できれば復元された七尾城の本丸会所で食べたいな…と思う。
(4)資料から読み取れるもの
(著作権上無断転載はおやめください。)
この資料を私畠山義綱が、林光明殿にお見せして、色々ご教授を頂きました。せっかく色々ご教授頂いたので、ここにそのメール対談の一端を抜粋してアップします(♯文面の都合上、発言の修正・追加などを行った)。
- 林六郎光明殿
- これは大変な歓待だというのが率直な感想です。まず、廿一献まで進むと言うのは、宴会でもかなり大規模なものです。永禄当時、室町幕府でさえ、ここまで大規模な宴会と演能はなされていませんから、いくら地元の猿楽師の者とは言え、大変な盛会だったことは疑う余地もありません。演能の順番にも、ちゃんとした式次第がありまして、それをきちんと踏まえていますし、さすがと言わざるを得ません!
- 畠山匠作源義綱
- この「○○殿御使」というところは、義綱(主君)に対する贈り物した記録なんですね。凄いものを送っていますね。
- 林六郎光明殿
- 式三献のところの「直御馬御太刀栗毛」は長続連が直(じか)に、という意味でしょうし、初献の「御太刀一腰供房」は、房つきの太刀1振り、五献の「源次郎殿御使」は披露した者の名前、「三河守殿あいそへ」は「相添え」で献上の手伝い、鎧具足3領に「御太刀一腰金ふくりん」は金覆輪(きんぷくりん)つまり黄金の拵えに金の金具で飾った太刀ですね。ときどき出てくる「盆」は、今の平べったいお盆じゃなくて、おそらく足付きの台になった盆のことでしょう。七献の「盆ニ直」は、「この盆にじかに乗せて」の意だと思います。このことから、それ以外の太刀は飾り台付きだったことがわかります。九献の「御絵一ふく盆筆馬遠」は、「盆に乗せた馬の絵の掛け軸1幅(1本)」、十一献の「御打刀景光」は「景光銘の大刀(太刀ではなく、今の日本刀)」、十三献の「御長刀法成寺」は、よくわかりませんが、おそらく薙刀ではなく、真柄の大太刀のような、かなり長い日本刀で「法成寺」と名づけられたものでしょう。面白いのは三献の「盃・香合」で、盃はともかく、香道や茶道の道具である香合が入っていることです。
- 畠山匠作源義綱
- 七尾城下町の発掘調査で文化を示す発掘として、香炉が出土
しており、七尾に香道が盛んに行われていたということが推測されています(都市としての「中世七尾都市圏」の発展参照)。すると、永禄期の畠山家でも香道などの文化は残っていたのですね。
- 林六郎光明殿
- この宴には大変な費用がかかっただろうと想像できます。長氏の財力の凄まじさの一端を見る思いです。
- 畠山匠作源義綱
- この大規模な歓待も長続連が払ったのだとすると、財力もさる事ながら、能の順番など続連の文化水準が見て取れるのですね。「長家文書雑記」の記録なので、話半分に考えても相当の宴会なんですね!畠山の晩年期には全く文化的業績無しのように言われますが、この事から晩年の畠山家中の文化水準が伺えますね!!
- 林六郎光明殿
- 文化水準の高い殿様を歓待しようと思ったら、下手な宴会では逆に怒られてしまいますからね。ですから、殿様の水準が高いということは、周囲も必然的に水準を高くせざるを得ないのですよ。畠山氏だけが突出して高いということはありえないですね。このあたり、他の成り上がり戦国大名とは違うところです!
- 畠山匠作源義綱
- 永禄九年の政変で追放された畠山義綱が曲直瀬道三に医道の伝授を受けて、見事相伝に成功したこと等と併せていくら戦乱で荒れていたとはいえ、畠山家の文化水準は決して落ちていなかった事は確かですね。もっと戦国期の文化的業績にも注目してもらいたいです。今川氏真など文化に精通した人物はまるで凡将扱いですからね・・・。
- 林六郎光明殿
- この時期の大名の文化と言うと、軽視されがちですけれども、彼らの後世に与えた影響というものは、かなり大きいと思っています。秀吉の代になって「天下一」という称号をいろいろな名人上手に与えていますが、彼ら文人大名が営々と育成してきたからこそ、そういう人々が平和になってから輩出して、あの華麗な桃山文化や江戸初期の豪壮な文化に繋がっていったわけです。
ですからこういう史料は、ただ宴会の様子を伝えるものではなくて、それまでの文化的業績の積み重ねの上にある、1つの結果例であると考えるべきと思っています。
長続連の義綱歓待について、林光明殿にご教授頂いた要点をまとめると、以下のようになる。
(1)廿一献まで進むという宴会でもかなり大規模なもので、演能の順番などからして、長続連の文化水準と財力の高さが知られる。
(2)この歓待から、畠山氏晩年の文化水準が依然高いものである事が伺われる。
(3)室町時代の文人大名の文化芸能が、平和な時代になってから輩出して、あの華麗な桃山文化や江戸初期の豪壮な文化に繋がっていった。
という事がこの資料から読み取れる。戦国時代はその戦乱の時代から政治的な業績に脚光が浴びてしまいがちであるが、こういった文化にも脚光をあてて、その文化変遷を感じとっていきたいものである。
(4)献立について
2006(平成18)年に刊行された『新修七尾市史』七尾城編と、2016(平成28)年に刊行された『加能登資料ⅩⅣ』に、『長家文書雑記』の献立メニューを含めたすべての宴会内容が記載されていたのでそれを抜粋した。これによると料理の内容も大変豪華である。能登は半島であるゆえ、漁業も盛んであったろう事から、海産物の料理が多いのもうなづける。現代でも能登ではアオリイカが有名であるし、富山湾の鰤有名である。さらに海鼠腸、タコ、カツオ、アワビなどなど海産物に関しては枚挙にいとまがないほどである。また、食事の合間合間にあつ物(吸物)が出てくるもの誠に豪華であると言える。
現代的価値観から意外と思うのは、魚以外にも鳥類の肉が多いこと。動物性タンパク質の摂取が少なかった室町・戦国時代の武将だが、その重要性は当時の医学書でも指摘されており、栄養学的な見地からも動物性タンパク質を取るために必要だったのであろう。
越前朝倉氏の城下町である一乗谷史跡からは様々な武家屋敷や町人の建物などの遺構が発見され注目を集めたが、発掘されたのは屋敷跡などばかりでなく、動物の骨も見つかっている。それは自然死によるものばかりではなく、食膳に上がったものであると考えられる。能登も越前も北陸で日本海に面しているということで共通点が多い。そこで一乗谷史跡でみつかった食材との共通点を見ていく。まず一乗谷史跡でも多く見つかったアワビ類は海の貝であり日本海で獲れたものであろう。サメ・スズキ・ブリ・フグも一乗谷史跡で見つかっている。どれも日本海の代表的な魚である。また、一乗谷でも淡水魚であるコイも見つかっている。豊富な海魚がある中でコイが共通しているということは、好んで食べられたということだろうか。ただ、カツオは一乗谷史跡では見つかっていない。カツオは太平洋側での漁獲が多く、日本海で水揚げされるのは稀と言われる。富山湾にもカツオが揚がらないではないが、沢山は獲れないと言う。ヒシクイはカモ科に属し、日本海に多く生息する鳥である。一乗谷でも食されたと見え、史跡で骨が発掘されている。こう見ていくと、一乗谷史跡との共通点も多く見え、食事の種類はおおよそ中世の能登で食べられた食材であることが確認された。中世能登の生活を知る上でも非常に貴重な史料であると言える。
また、東四柳氏によると(金沢学院大学文化財学科主催の平成19年度公開講座「半島能登の風土と歴史―食文化を中心に―」七尾サンライフプラザにて開催)、「文書にみられる「から島のり」は中島町の島でとれる海苔、「松百すし」は、七尾の松百の熟れずし、というように、地域名が入った食材は、すでに地域ブランドとなっていたものといえよう。」とすでに中世室町時代で、海産物の干物・塩漬けなど保存・加工技術が進んでいることを指摘している。
このように、能登の豊富な海産物は贈答品としてだけでなく、能登国外への貿易品としていたことは容易に想像できる。これらの産品が能登の経済を潤わせていたのであろう。
★参考資料

式三献の様子 「花揃春対面」歌川国貞(二代)画、1868(明治元)年<国立国会図書館所蔵>
(注釈)
(注1)松百すしについて、『能登畠山文化源流をゆく2018年度調査報告書に』(P.105)に詳しいので以下転載します。
松百すしの初見は1552(天文21)年で、温井総貞が本願寺へ鱈や背腸とともに贈っている(天文日記)。『料理無言抄』には「松百鮓、一名松百之蛇鮓ト云、いさき魚ヲ以製ス、能州松百之名物也」とある(米田尚史編・見瀬和雄校訂『料理無言抄』能登印刷出版部2016)いさきは淡水魚である。(転載終了)
(注2)「この日吉大夫が近江猿楽である事は、其の一座に嵐大夫が存する事より見て断言し得る所である。」(『能楽源流考』より」
- 参考文献
- 片岡樹裏人『七尾城の歴史』七尾城歴史刊行会,1968年
歴史書刊行会(編)『加賀能登の能楽』北國新聞社.1997年
東四柳史明(他共著)『社寺造営の政治史』思文閣出版,2000年
『越前朝倉氏一乗谷-眠りからさめた戦国の城下町-』福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館,2005年
『能登畠山文化源流をゆく2018年度調査報告書』(共著)のと共栄信用金庫,2019年
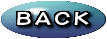
不定期特集目次へ戻る
Copyright:2023 by mitsuaki hayashi & yoshitsuna hatakeyama -All Rights
Reserved-
contents & HTML:yoshitsuna hatakeyama

