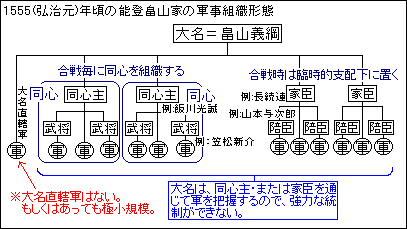能登畠山氏の軍事組織における考察
| 能登畠山氏が大名であったからには、当然組織的に戦争が行われ、そのために兵隊が集められた。ということは、戦時に備えて軍事体制が組織的にあったわけであり、どのような体制で軍事組織が作られたのか、その様子を少しでも明らかにしていきたい。 |
(1)基本的な軍事組織
能登畠山家の軍事組織はどうであったのか。それを専門に論評する論文は皆無である。しかし東四柳史明氏が、畠山義綱の人物像を明らかにする上で、その時代に多く見られる能登での錯乱における合戦関係の書状から、軍事組織について述べている(東四柳史明「畠山義綱考−能登畠山氏末期の領国体制−」『国史学』88号.1972年)。
その論文によると、弘治の内乱時、在地社寺勢力が積極的に義綱軍の支援をしていたが、これは義綱が内乱終結後の積極的保護を約束して味方にした結果である。そのために戦後に義綱専制体制が確立すると義綱は積極的に社寺に寄進を行った。また、「能登畠山氏の場合、有力戦国大名の軍事組織である寄親・寄子方式は見い出せない。同氏の軍事力の基盤が、領国内有力国人層(重臣)の持つ独立した一族・被官組織と、有力国人を同心主として中小国人層等を臨時的に大名権力の下に組織化した同陣・同心方式であったことは、畠山氏一族の存在が領国内から多く検出できず、その直轄軍が接見し得ないことと共に、同氏権力基盤の内部に、軍事力の側から重臣層の抬頭を許容する要因が、内包されていたことを指摘できる。」と述べている(東四柳氏前掲書.29頁より)
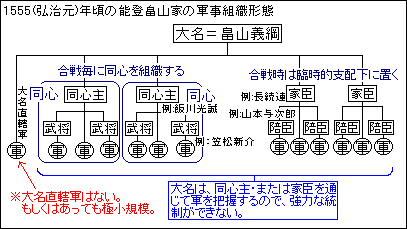
なぜ寄親・寄子方式ではないのか。東四柳氏の指摘は以下の古文書から指摘している。
(古文書A)飯川光誠書状写(笠松文書)<1547(天文16)年>
至ニ于端郡押水一、(畠山)駿河殿一戦之刻分射、則駿河殿被渡相、太刀討、太刀疵被レ疵候。無ニ比類一御高名ニ候。弥向後御心懸肝要候。恐々謹言。
(天文十六年)
壬七月七日 |
|
笠松新介殿
御宿所 |
飯川主計助
光誠(花押) |
|
|
(古文書B)温井総貞書状写(笠松文書)<1550(天文19)年>
去廿六日於遊左馬之下口被討、可然矢無比類御働之由候、御高名之至無是非候、彌御馳走肝要候、恐々謹言。
(天文十九年ヵ)
十月廿九日 |
温井備中守
総貞(花押影) |
笠松新介殿
御宿所 |
|
|
|
古文書(C)長続連軍忠感書 「山本文書」
去晦日於二留雲首一最前責上、能矢仕、被二鑓疵一ヶ所矢手一ヶ所一、粉骨之働無二比類一、誠神妙之至候。弥可レ励二忠節一事専一候。恐々。
山本与次郎殿 |
|
|
戦時において大名権力の下に臨時的に組織化した「同陣・同心方式」に比べて、寄親・寄子方式は主従関係の安定のために寄親・寄子という被官関係は原則的に固定化している。寄親(重臣)は寄子を固定化することにより、被官関係を築きより強固な関係を築き、命令系統や軍事的動員力を安定化させる効果がある。また、大名にとっても寄親が力を持ち、その寄親との関係を強固に結んでおけば大名自身の支配も安定し、寄子の間接的な支配も安定化する。しかし、同陣・同心方式では、あくまで臨時的に組織化するものであり、その主従関係は合戦ごとに変化する可能性がある。すると関係が安定化しないので、大名の間接支配も弱まり、結果個々の力が強まるのである。
古文書A・Bは両方とも笠松但馬守に対する感状である。古文書Aは1547(天文16)年における押水の合戦時のものであり、古文書Bは1550(天文19)年の能登天文の内乱時のものである。文末が「恐々謹言」と丁寧であることから、発給者と受給者との間に被官関係は考えられない。また、古文書Aと古文書Bと違う合戦で発給者が変化していることから、能登畠山氏の軍事組織が、寄親・寄子方式でなく、同陣・同心方式と考えられている。また、古文書Cは長続連が山本与次郎に与えた年次不詳の感状である(注1)。文末が「恐々」とあることからも、発給者と受給者との間に被官関係が認められる。能登畠山氏の軍事組織が古文書A・Bに見た同陣・同心方式であるから、この古文書Cだけで、長続連が山本与次郎の関係が寄親・寄子方式とは言えない。むしろ長続連が16世紀中頃まで室町将軍の奉公衆として能登国内で能登畠山氏が独立した立場をとっていたことを考えると、この両者の関係は長続連の個人的な被官関係の可能性の方が高い。これが東四柳氏が言う「領国内有力国人層(重臣)の持つ独立した一族・被官組織」の軍事組織体制である。
(2)大名直轄軍の存在
東四柳氏は「畠山氏一族の存在が領国内から多く検出できず、その直轄軍が接見し得ない」と指摘した。「直轄軍が接見し得ないことと共に、同氏権力基盤の内部に、軍事力の側から重臣層の抬頭を許容する要因が、内包されていた」と問題点があるにも関わらず、なぜ能登畠山氏の大名直轄軍は存在しないのか(あるいは、あったとしても極小規模だったのか)。その理由を考察してみたい。
主君が大きな直轄軍を持たなかったというのは、この時代の室町将軍も同じである。「幕府の首長である将軍のもとには「奉公衆」と称される将軍直臣を中核にした、およそ千〜二千人規模と推定される直轄軍が置かれていた。しかし、この程度の規模の直属軍だけでは大規模な謀反の発生といった重大事変には十分に対処することができない。そこで、重大事変が発生した際には将軍から守護たる大名たちに出陣命令が下され、これら大名たちの軍勢とが将軍の指揮のもとに合同して事変に対処する、ということになっていた。」(山田康弘『『戦国時代の足利将軍』吉川弘文館.2011年,12頁より)と、あるように、室町幕府の軍事組織も、基本的に同陣・同心方式と言える。つまり直轄軍は小規模で家臣の軍事力を臨時的に組織化する体制が、当時の主流ではあったのではないだろうか。しかし、この構造は、先に東四柳氏も指摘したように、家臣たちの協力を受けなければならず「重臣層の抬頭を許容する要因」となりうる。どうしてこのような存立の仕組みになったのかについて、山田氏は「「大名たちが将軍への協力を拒否する」などという事態がそもそも想定さてていなかったと判断される」(前掲書,15頁より)と指摘している。なぜその事態が想定されていなかったとの問いには「大名たちは「将軍あっての大名」であったわけであり、それゆえに多くの大名たちは、将軍の上意が下されたならばこれを簡単に拒否しにくく、将軍から協力を命じられたならばこれに応じざるをえない、という立場にあった。」(前掲書,19頁より)としている。
基本的に、守護とその被官の軍事組織も同じような理由で、直轄軍が極小規模で家臣の動員兵力に頼るという構図ができたと思われる。また、室町時代前期は守護は在京が原則とされていたのも直轄軍が小規模だった理由だと思われる。京都の町に大規模な直轄軍を常駐させるのは、物理的にも経済的にも難しい。国元に直轄軍を置いておいたとしても、守護代に掌握されてしまう危険性もある。そもそも、室町時代には常設軍という存在があまり農閑期に軍隊を臨時的に組織する形式が多いので、大名は指揮権のみを有し、被官が実働部隊を臨時的にかき集める形式が定着し、それが戦国時代になって被官の相対的軍事力強化=下剋上の下地をもたらしたのではないか。しかし、まったく能登畠山氏において大名直轄軍がなかったとも言えない。その理由を能登畠山氏4・6代当主・畠山義元の事例から見てみよう。
畠山義元は弟である畠山慶致と取合(兄弟ゲンカ)を起こし、能登明応九年の政変にて、守護を追われた。その後両者和解をし、兄・義元が守護還任した後、比較的すぐに上洛した。1509(永正6)年12月には将軍足利義稙邸で「猿楽」を細川高国・大内義興らと共に鑑賞している。また、1511(永正8)年8月24日に足利義稙が京舟岡山で将軍義稙・細川高国が政敵である前将軍・義澄・細川澄元等の敵軍を破った合戦(舟岡山合戦)では、「尚通公記」によると「公方衆二千人計、細川右京兆(高国)三千人計、大内左京兆(義興)衆八千人計、畠山修理大夫(義元)衆三百人計、都合一万五六千計」としているなど、義元は義稙軍の主力として参加している。
この「舟岡山合戦」で、義元は300人の兵を動員している。細川高国が3000人、大内義興が8000人と比べると異常な少なさである。元々の領国の広さや経済力を考えると仕方ないのかもしれないが、ともすればこの300人は「義元が京都ですぐに動員可能だった兵力」と考えることもできる。ということは、この300人が大名直轄軍ではなかろうか。すると、能登畠山氏が在国している時にも300人程度の直轄軍はいたのではないか。しかし、300人程度では重臣の兵力に勝てるほどのものではなく、「直轄軍はあったとしても極小規模」という言葉は的を得ているのではないか。
(3)「能登畠山家自壊」の遠因
能登永禄九年の政変とは、1566(永禄9)年に起きた守護の畠山義綱が父・畠山義続や義綱派の家臣と共に長続連、遊佐続光、八代俊盛らに追放される事件である。義綱は能登弘治の内乱(1555年〜)で勝利し、大名専制政治を確立した。この内乱では反乱勢力との力が均衡していた。戦力を簡単に増強させるには、寺社や国人層との深い関係を結んでいる人物を味方につけることである。そのため下野していた遊佐続光を帰参させることで戦力増強を図ったのである。義綱の領国再編期(1555年〜1566年)の改革は、義綱側近である奉行人を中心に政治が運営されており、先の内乱で活躍した長続連・遊佐続光ら政変の首謀者ら年寄衆は当主・義綱の補佐に甘んじていたのである。さらに、義綱は側近の飯川光誠を年寄衆にしてその中心的な役割を担わせ、他の年寄衆の権力を抑制していた。しかし、この義綱の改革には能登畠山氏の政治体制が抱える内的矛盾と言うか限界があった。それは、大名直轄軍が存在しないということである(詳しくは畠山義綱特集参照)。即ち重臣の軍事力に支えられている能登畠山氏は、強力なリーダーシップを採れる軍事的背景が大名には存在しないので、重臣権力削減には重臣の同意が必要という内的矛盾を包括しているのであった。それゆえ弘治の内乱で専制支配を確立した義綱であったが、領国改革・再編においても長続連、帰参を許した遊佐続光たち重臣らに配慮する事が求められたのである。そしてさらに一層の大名権力拡大を狙うと重臣たちの猛反発に遭い、追放されてしまうという憂き目にあってしまったのである。
この政変で義綱は、能登から脱出して近江へ亡命した。大名直轄軍が大規模に存在するならば能登国内で抵抗することもできるし、第一政変が起こった段階で直轄軍が抵抗する。しかし、そういった大規模な反乱がなく義綱自身が近江へ亡命している事実から考えると、やはり大名直轄軍の存在は極小規模であり、先に見えるように300人程度のものであったのかもしれない。また、寄親・寄子方式が能登に定着していたなら、主従関係も安定し、寄親は寄子を安定するために大名権力に依存せざるを得ず、このような政変も起こらなかったのかもしれない。
このように、能登畠山氏の軍事組織が大名直轄軍の存在だけではなく、戦国大名に一般的にみられる寄親・寄子方式の定着がなかったゆえに、常に能登畠山家は軍事的に不安定でありこのような政変劇が生まれた要因になったのではなかろうか。この結果、重臣たち「パワーオブバランス(勢力均衡)」を図るようになり、畠山義続政権で畠山七人衆政治(詳しくは「畠山七人衆体制と権力闘争」参照)が誕生してしまったり、長派、遊佐派、温井派といった派閥政治(詳しくは「畠山家晩年における政治体制の一考察」参照)が畠山義慶・義隆政権の下で展開されてしまい、一層の大名権力低下を招いたと考えられる。これが、能登畠山家が自壊してしまった遠因と言える。
(註釈)
(注1)時期は1569(永禄12)年の鶏塚の合戦のものとも言われているが、確定的とは言えない。
- 参考文献
- 東四柳史明「畠山義綱考−能登畠山氏末期の領国体制−」『国史学』88号.1972年
山田康弘『戦国時代の足利将軍』吉川弘文館.2011年
etc・・・
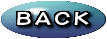
不定期特集目次へ戻る
Copyright:2011 by yoshitsuna hatakeyama -All
Rights Reserved-
contents & HTML:yoshitsuna hatakeyama