人物列伝
「武田義統」

↑武田義統イメージ像(畠山義綱画)
| 人物名 |
武田 義統(たけだ よしずみ) |
| 生没年 |
1526〜1567 |
| 所属 |
若狭武田家 |
| 主な役職 |
若狭武田家当主 |
| 参考文献 |
黒崎文夫「若狭武田氏の消長」『一乗谷史学』12号
水藤真「武田氏の若狭支配」『国立歴史民俗博物館研究報告』2集
米原正義「若狭武田氏の文芸」『日本歴史』257号 |
- 人物の歴史
- 信豊の嫡男。幼名彦ニ郎。治部少輔、伊豆守、大膳大夫。若狭武田氏は15C末〜16C初めの元信の時代に最盛期を迎える。連歌など歌道に精通し、また伊勢物語や古今集なども読んでおり文化に精通していた。その一方、元信は騎射なども巧く、「武家故実」を元信が作成していることから考えると、元信が文武両道の良将であったと考えられる。また、武田氏領内には京都と北陸を結ぶ日本海交通の若狭の港・小浜がある。同地は港町として発展し、流通を武田氏が掌握する事によって武田家は潤っていたに違いないと思われる。しかし、その若狭武田家も、天文年間にはその勢いを弱めていった。
武田義統はいくら戦国の世といえども、父とも子とも争った珍しい人物である。まず1556(弘治2)年に、若狭武田家で内乱が起こる。それは、義統の父・信豊と、信豊の弟・重信と義統の三者の家督相続争いである。重信の支持派として若狭武田氏の筆頭重臣・粟屋氏の勝久がいた。しかし、重信派が争いに敗れると、勝久はその文化的水準の高さを利用して今川氏真を頼って逃げて行った。そして翌々年(1558)、ついに義統とその父・信豊の争いが起り、信豊軍が近江まで進出していたのが伺える。これにより、信豊が家督争いの時期にすでに若狭より避難して対峙していたことになる。この争いは、近江六角氏の調停により矛が収められ、同年(永禄元)12月13日には義統の西福寺に対する安堵状が見られるので、この頃までには義統が家督を継承していたようである。義統の治世に関する史料は乏しい。しかし、義統政権になっても政情は安定せず、重信はとして一旦は若狭を退いた粟屋勝久が再び反乱を起こした。すでに、この頃、武田氏に粟屋氏の反乱を押える力が無かったようで、隣国の朝倉氏の応援を頼み、この内乱を鎮圧している。この事を表して黒崎文夫氏は「若狭武田氏の消長」において「自己の家臣を統制できない当主・すでに勝久の勢力は、武田氏を上回っていたといえる。」としている。義統は朝倉氏の支援で粟屋氏を追討した一方、同じく反旗を翻した逸見氏に対しては自軍を率いて追討している。逸見氏得意の水軍戦で自ら水軍を編成しこれを破るなど、義統は一応家臣の追討に成功していた。しかし、義統の頃になって内乱が続いた為か、歴代若狭武田氏当主と比べて義統の発給文書(特に寄進行為)が激減し、義統時代にはすでに若狭武田氏の昔日の勢いはなく、義統の領国運営は困難を極めていたことを裏付ける。この状態を乗り切る義統は朝廷に頻繁に貢物を送っている。これは、朝廷の権威を利用し、大名としての自分の地位を高めようとしている事実が垣間見える。このような状況であったため、父・信豊の時代まで当主の「武家故実」が知られるが、義統には見られない。およそ、文武芸に興じる余裕すらなかったであろう。
その後、1566年(永禄9)13代将軍足利義輝が暗殺された事で、その弟・義秋が姉婿である義統を頼りに若狭武田氏の下へ小浜にやってきた。しかし、『多聞院日記』にあるように「若狭モ武田殿父子及合乱逆ト云々」とあって、義統とその子・元明(1552-1582)が家督争いをしていた状況が伺える。若狭が内乱状態であったので、当然足利義秋に手助けできるはずもなく、義秋はその後、朝倉氏を頼って越前に行ってしまう。結局、1567年に義統が死去した事で武田氏の家督は元明が継いだ。さらにその翌年(1568)には越前朝倉氏が若狭に侵攻し、武田家は滅亡する。最後の当主・元明は何故か殺されず、朝倉に保護され一乗谷に連行され生き延びたのであった。こうして、戦国大名化を遂げつつあった若狭武田氏も滅亡してしまうのであった。
- 義綱解説
- 武田氏と言うと真っ先に思い浮かべるのが甲斐の武田氏です。それは、江戸時代でも同様であったようで、若狭武田氏の多くの「故実書」もその時代の人々は「武田之信玄歴代名将の記録巻物」甲斐の武田氏のものと認識している。私はどうしてもマイナー好きなので、有名な甲斐の武田氏よりもどうしても若狭武田氏を応援してしまいます(笑)黒崎文夫氏も前掲論文で、朝倉氏の研究が飛躍的に進むのに、若狭武田氏の研究はいっこうに進まないと言っているように、非常に若狭武田氏研究は遅れているようです。最近では『小浜市史』等自治体史に若狭武田氏の項があるようですが、一層の研究を期待しています。
☆信長の野望で武田義統能力値の変遷
政=政治。戦=戦闘。武=武勇。知=知略・智謀。采=采配。統=統率。外=外政。魅=魅力。教=教養。野=野望。健=健康。運=運。足=足軽適性。騎=騎馬適性。鉄=鉄砲適性。水軍=水軍適性。弓=弓適性。計=計略適性。兵=兵器適性。城=築城適性。内=内政適性。
全国版の数値はMAX=106。数値はゲームの過程で上限を超えて変動。
天翔記の数値は政治、戦闘、智謀のみMAX=200、それ以外はMAX=100
♯全国版のみ「知能」を「政治」に、「野心」を「野望」の能力値に置き換えた。
♯蒼天録以前は「知略」は「智謀」であった。
| ゲーム |
政 |
戦 |
武 |
知 |
采 |
統 |
外 |
魅 |
教 |
野 |
能力適性 |
特技・策戦 |
個性 |
志 |
| 足 |
騎 |
鉄 |
水 |
弓 |
兵 |
| 天翔記 |
106 |
102 |
− |
60 |
− |
− |
− |
75 |
− |
49 |
D |
D |
E |
E |
− |
− |
− |
− |
− |
| 烈風伝 |
49 |
36 |
− |
43 |
51 |
− |
− |
− |
− |
− |
D |
D |
E |
E |
− |
− |
− |
− |
− |
| 嵐世紀 |
42 |
− |
− |
32 |
− |
39 |
− |
− |
− |
32 |
足軽・騎馬・槍 |
− |
− |
守戦 |
− |
− |
| 蒼天録 |
38 |
− |
− |
31 |
− |
35 |
− |
− |
− |
43 |
足軽・騎馬 |
− |
− |
威圧・鼓舞 |
− |
− |
| 天道 |
40 |
− |
61 |
43 |
− |
71 |
− |
− |
− |
− |
C |
D |
B |
− |
D |
D |
連撃之一 |
− |
− |
| 創造 |
44 |
− |
60 |
47 |
− |
64 |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
鬨の声 |
− |
− |
| 大志 |
44 |
− |
59 |
49 |
− |
62 |
43 |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
気勢崩し・神出鬼没 |
守城心得・検地奉行 |
領地保全 |
義統の能力はパッとしない。しかも将星禄での若狭武田家は、大名家としての登場ではなく独立勢力扱いで義統は登場せず、義統の子の武田元明のみが登場するというおそまつさ。将星禄・烈風伝ではマイナー大名に非常に冷たく酷い扱いをしている。しかし、「嵐世紀」で見事復活登場。ただ、能力値差別化の為か能力値が下がった。蒼天録では若狭武田氏のみならず安芸武田氏まで登場し、甲斐武田FAN以外の武田FANを魅了したが、天下創世・革新では再び武将が削られ若狭武田氏は削除された…。そして、2009年久々の「天道」にて久々の登場するも、若狭武田氏の大名としてではなく、将軍・足利氏の家臣として(悲哀)。確かに若狭武田氏は足利氏によく従っていたが、まさか家臣としての登場とは…。2013年発売信長の野望創造にて若狭武田家復活!義統も大名としての登場です。
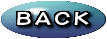
「人物列伝」の目次へ戻る
Copyright:2018 by yoshitsuna hatakeyama -All Rights Reserved-
contents & HTML:yoshitsuna hatakeyama

