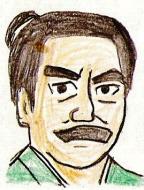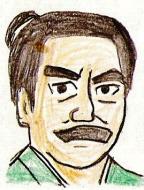人物列伝
「畠山高政」
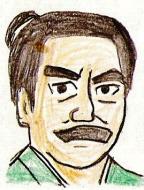
↑畠山高政イメージ像(畠山義綱画)
| 人物名 |
畠山 高政(はたけやま たかまさ) |
| 生没年 |
1527〜1576 |
| 所属 |
河内畠山家(畠山尾州家・政長流) |
| 主な役職 |
河内畠山家当主 |
| 特徴 |
何度も転戦を繰り返し実力を取り戻そうとする。 |
- 人物の歴史
- 播磨守。尾張守。仮名・次郎四郎。河内守護。1552(天文21)年9月29日条の『天文日記』によると、「畠山家督次郎四郎(高政)播磨守子也、就被成之、以一札太刀、馬代遣之使円山。」とあり、この時期に河内畠山で代替わりがあったことがわかる。従来は、1550(天文19)年に畠山政国が死去したことが家督交代と見られていたが、当時代の一級史料である『天文日記』に書かれていたことは、信用ができる。
さて、この頃の河内畠山氏は将軍家や細川家、三好家との離合集散を繰り返していた。そのため守護代遊佐家も影響力を強めるために、従来からの遊佐氏の被官である萱振氏や走井氏等に加え、菱木氏や草部氏などの畠山氏内衆も家臣化していき、鷹山氏、安見氏などの小領主も遊佐の被官に組み込まれている。一元的に主体的な支配を行っていた能登畠山氏とは違い、中央政争に巻き込まれる形で、守護代遊佐氏の影響力が大きくなっていた。それゆえ家中での政争も多く、家督が変わった前年にはすでに河内畠山家中には不穏な事件が起こった。畠山稙長政権や畠山晴熈政権の実力者であり、三好長慶と自分の娘を結婚されるなど畿内でも実力を得ていた遊佐長教が1551(天文20)年5月5日に暗殺された。下手人は坊主であったが、裏で指示していたのが河内の富豪で実力者でもあった萱振氏と言われている。河内畠山家内部、それも守護代遊佐氏内部での深刻な対立が起きた結果と言える。
この遊佐長教の暗殺の結果、畠山家中は、萱振賢継を中心とするグループと、守護代遊佐家の家臣で私部城主であった安見宗房(やすみむねふさ)のグループに分裂した。この対立に三好長慶が遊佐長教の婿として仲裁し、宗房の息子・宗泰と萱振賢継の娘を結婚させることで和解させた。しかし、翌1552(天文21)2月10日には宗房は河内郡代の萱振賢継らの一族を酒宴に招き暗殺し、さらに田河氏、中小路氏らだけでなく畠山氏の内衆である野尻氏すらも粛清をおこなっている。さらに宗房は野尻氏に自分の子を養子にし、その所領を自領化している。遊佐長教の暗殺をきっかけに河内畠山氏の実力者は大きく転換したのである。そして畠山家の内衆である丹下盛知や守護代遊佐家の内衆である走井氏の協力を得て家臣団の統制に成功した安見宗房は、正当な管領家の継承者を周囲にアピールするために畠山高政を守護に擁立したのである。守護代家の跡目は遊佐太藤が安見宗房や丹下盛知や走井盛秀らによって擁立された。高政政権下の1553年(天文22)年に発給された文書には、丹下盛知とその下に安見宗房の連署状がある。家中での実力はともかく、家格としては畠山家の内衆での丹下盛知、守護代家内衆の安見宗房という順位だったと言え、この2人が政権の中枢を担ったのだろうと推測できる。
高政の外交方針は、基本的に将軍・足利義輝に味方し、三好氏と対立する方向性であった。1553(天文22)年、反幕府方・三好長慶と将軍・足利義輝・細川晴元の軍勢が京都一帯で戦った。河内畠山氏は7月に三好方として宗房と盛知が長坂・舟岡あたりで戦っている。同年8月には三好長慶と共に上洛している。この後も宗房は1556(弘治2)年に大和の畠山尚誠や鷹山氏を攻め大和での基盤を確立した。1558(永禄)年間になると遊佐太藤の名が見られなくなる。これは、死没とみる専門家もいるし、高政が排除し、新次郎(後の教、信教)を用いたと見る専門家もいる。もし、高政が太藤を排除したとするならこの時期に主体的に家臣組織を操作し得るほど権力が回復していることを示唆することになる。
こうして守護代嫡家の勢力に陰りが見られる状況で、実質的にも安見宗房が守護代家にとって代わる行動をしていたようである。江戸時代に成立した軍記物などの二次資料によると1558(永禄元)年11月には高政が安見宗房の専横に怒り紀州に下った(一説には当主を降ろされたとも)言われる。おそらく、高政と家中の実権を巡る宗房との対立が本格化したのであろうと思われる。同年5月から三好長慶と足利義輝が何度も交戦しているが、三好方の勢力に河内勢が見られない。これは、河内畠山家中の対立が深刻化して加勢する状況になかったのでないか。
河内での情勢不安定は、三好長慶にも影響を与え、1558(永禄元)年11月将軍と和睦することになった。そして、河内畠山家の状況を立て直すために、長慶は紀伊に逃れた高政の復帰を画策し、安見宗房を高屋城・飯盛城から追放し、1559(永禄2)年8月高屋城に高政が復帰した(「観心寺文書」でも高政復帰が確認できる)。「細川両家記」には「畠山方と三好方一味」とあり、河内高屋城で高政が河内を支配することが定められた。
1559(永禄2)年9月に真観寺に高政が免税の判物を発給している。1545(天文14)年に畠山稙長が死去した後は、遊佐長教が発給していたことを考えると、高政が大名権力が回復を企図していた見える。しかし、高政の河内支配は安定したものではなかったようだ。河内の将軍御料所の年貢納入は三好氏が仲介したようで、外部勢力の介入が必要な程脆弱であった。それは、安見宗房など遊佐一族は地元の国人らと関係を強固に結んでおり、宗房の影響力が河内畠山家中の深くまで浸透した結果と言える。大名権力の安定化を考える高政と、家中に影響力が依然存在し、家中復帰を企図する宗房との思惑が一致した。1560(永禄3)年6月に高政は三好に無断で安見宗房と和与した。
このような離合集散が畿内の政争を複雑化することになる。安見宗房を排除することで河内畠山氏の安定を図ろうと考えた三好長慶がこの和議を結ぶ事を快く思うはずがなく、三好長慶は和睦を理由に河内へと出陣する。同年6月29日には河内中部に進出し、飯盛城の安見宗房と高屋城の高政を分断。8月6日には三好実休が石川郡に進出し、畠山方の一揆を制圧。8月14日には堀溝(大阪府寝屋川区)で宗房の軍を破った。さらに元々は将軍の奉公衆だった湯河氏の直光は、畠山家宮内少輔家を継承し畠山家に味方していたが、長慶はその湯河氏にも畠山氏からの離反を迫っていた。この頃から、長慶は高政に安見宗房の追放を迫るのではなく、畠山家自体を河内から追放し、直轄地にする方針だったのではないかと思われる。そして10月には高屋城・飯盛城が陥落し、高政らは堺へと出奔した。この後長慶は飯盛城を本拠地とし、歴代畠山氏の居城であった高屋城は三好実休を入城させ、本格的な支配を展開している。
高政は六角承禎と組み河内奪回のために根来寺・湯河直光などの紀州勢を率いて1561(永禄4)年7月には河内に進撃する。この戦いは長期戦となり翌年まで及ぶ。1562(永禄5)年3月5日の和泉久米田合戦で、三好実休を戦死させ、念願だった高屋城を奪還した。さらに六角氏が京都を占領したこともあり合戦は高政に有利に進んだ。そして、高政軍は三好長慶の本拠地である飯盛城の攻撃を開始し、同年5月20日の河内教興寺合戦を迎えた。この合戦で四国衆を加えた三好軍に根来衆を加えた畠山軍は大敗する。主力の湯河直光が戦死し、安見宗房は大坂本願寺へ逃亡、高政自身は一端は堺へ逃れ、さらに紀伊へと逃れた。
1564(永禄7)年7月4日に三好長慶が死去すると、三好政権も弱体化していき。高政にも再び復権のチャンスが回ってくる。翌年1565(永禄8)年の10月頃より高政は再び河内方面へと進撃していく。弱体化していく三好家はこの動きを抑えられず、1566(永禄9)年に高政と三好家は再び和睦し高政が高屋城に復帰する。後に、織田信長が足利義昭を伴なって入京すると、三好家から離反し、信長に属して1568(永禄11)年に将軍・義昭より河内半国守護に任命された。だが、1569(永禄12)年に遊佐信教、安見宗房らの政権の中枢にある人物が高政の弟・昭高を擁立すると、岩室城に逃れ、1576(天正4)年に死去した。
- 参考文献
- 戦国合戦史研究会(編)『戦国合戦大事典第4巻大阪奈良和歌山三重』新人物往来社、1989年
弓倉弘年「天文年間の畠山氏」『和歌山県史研究』16号、1989年
矢田俊文「戦国期河内国畠山氏の文書発給と銭」『ヒストリア』131号、1991年
森田恭ニ『河内守護畠山氏の研究』近代文芸社、1993年
弓倉弘年「安見宗房と管領家畠山氏」(天野忠幸編『松永久秀』宮帯出版社、2017年所収)
天野忠幸『松永久秀と下剋上』平凡社,2018年
- 義綱解説
- この時期の河内畠山家は本当に複雑です。畠山尾州家(政長流)と畠山総州家(義就流)とが対立して、さらに尾州家家中の中でも対立構造があります。さらに、将軍家や細川家、三好家、本願寺との関係に加え六角家や紀州の根来寺や国人勢力など様々な支援勢力があり、畿内はまさに混沌としている状態でした。それゆえ、高政も状況に応じて色々な勢力と結ばなければ自家を保つことができないことがわかっていたようにも思えます。
☆信長の野望での畠山高政能力値の変遷
政=政治。戦=戦闘。武=武勇。知=知略・智謀。采=采配。統=統率。外=外政。魅=魅力。教=教養。野=野望。健=健康。運=運。足=足軽適性。騎=騎馬適性。鉄=鉄砲適性。水軍=水軍適性。弓=弓適性。計=計略適性。兵=兵器適性。城=築城適性。内=内政適性。
全国版の数値はMAX=106。数値はゲームの過程で上限を超えて変動。
天翔記の数値は政治、戦闘、智謀のみMAX=200、それ以外はMAX=100
♯全国版のみ「知能」を「政治」に、「野心」を「野望」の能力値に置き換えた。
♯蒼天録以前は「知略」は「智謀」であった。
| ゲーム |
所属 |
政 |
戦 |
武 |
知 |
采 |
統 |
外 |
魅 |
教 |
野 |
能力適性 |
特技・策戦 |
個性 |
志 |
| 足 |
騎 |
鉄 |
水 |
弓 |
計 |
兵 |
城 |
内 |
| 覇王伝 |
畠山家 |
41 |
59 |
− |
30 |
52 |
− |
− |
− |
− |
30 |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
| 天翔記 |
畠山家 |
118 |
92 |
− |
50 |
− |
− |
− |
72 |
− |
35 |
D |
E |
E |
E |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
| 将星録 |
三好家 |
55 |
41 |
− |
35 |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
D |
E |
E |
E |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
| 烈風伝 |
三好家 |
49 |
41 |
− |
25 |
39 |
− |
− |
− |
− |
− |
D |
D |
D |
E |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
| 蒼天録 |
畠山家 |
43 |
− |
− |
27 |
− |
30 |
− |
− |
− |
58 |
鉄砲 |
− |
− |
− |
− |
収拾・茶湯 |
− |
− |
| 創造 |
畠山家 |
22 |
− |
40 |
50 |
− |
34 |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
逆撫で |
− |
− |
| 大志 |
細川家 |
28 |
− |
40 |
51 |
− |
35 |
34 |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
臨戦・囮挑発 |
士気向上 |
所領拡大 |
高政は覇王伝で信長の野望初登場。中学生だった当時は能登の他にも畠山家がいるのだと、興奮したものです。その後、室町幕府の三管領の畠山の家柄と知ってさらに好きになりました。ただゲームにおける評価はイマイチですね。蒼天録で兵種が鉄砲なのは、おそらく和泉久米田合戦で三好実休(義賢)を鉄砲の流れ弾で討ち取ったことからきたのでしょう。その割に鉄砲適正は天翔記も将星録もE評価というのはどうなのでしょうか?。ゲームにおいて素晴らしいのはそのグラフィック。特に覇王伝で、とっても渋くてカッコイイオジサマです。畠山義綱と同時期に活躍した河内畠山家の人物ですから、もっと能力値も頑張ってもらいたいものです。蒼天録以来、登場武将の精選を受けて登場無し。しかし、創造で、しかも大名として復活を遂げる。ただ…政治値22ってちょっとひどいと思うのです。同じ時期の地方大名と比べてもかなり低いです。この混乱に次ぐ混乱の畿内で、一時的にしろ政権を保ったのは政治手腕だと思うのですが…。個人的には烈風伝の49が適正化と思います。
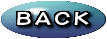
「人物列伝」の目次へ戻る
Copyright:2020 by yoshitsuna hatakeyama -All Rights Reserved-
contents & HTML:yoshitsuna hatakeyama